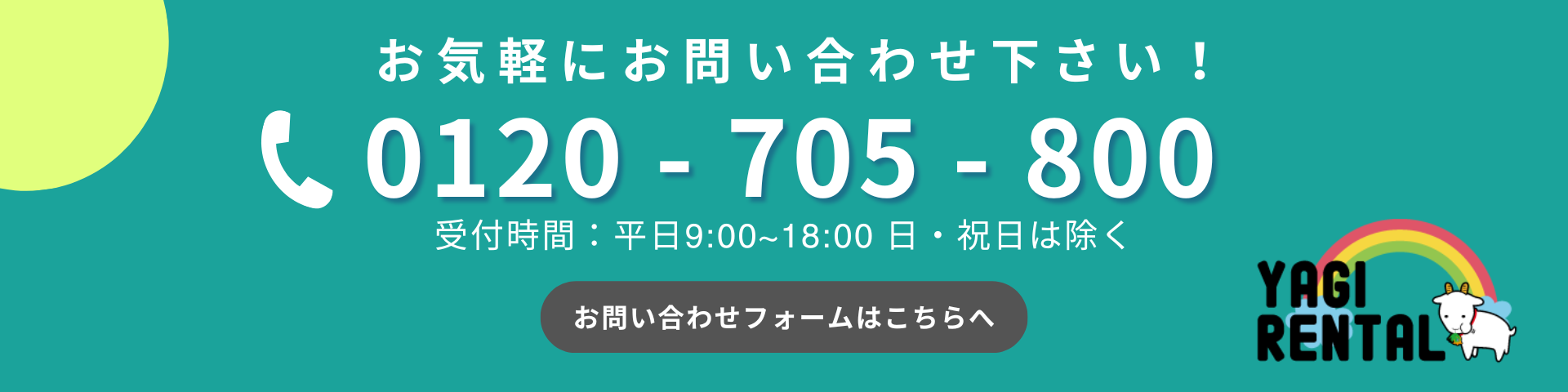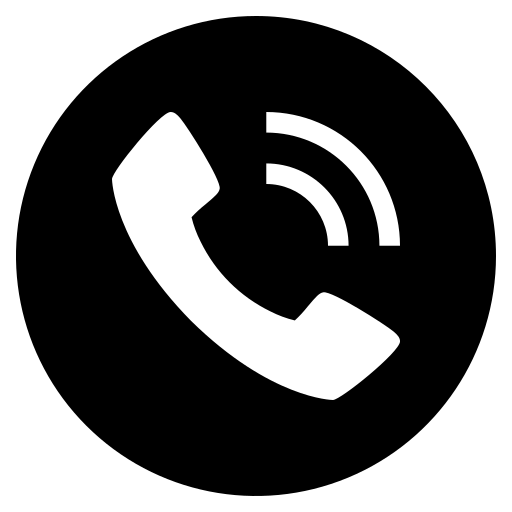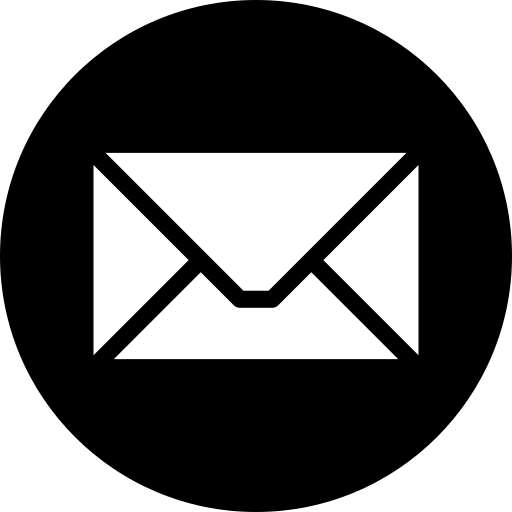晩秋のヤギ除草で来春が変わる ― 草管理と健康維持のコツ ―



10月から11月にかけて、草の成長がゆるやかになり、空気も冷たく澄んできます。 ヤギたちはこの時期、一年間の除草活動の“締めくくり”を迎えます。 晩秋の除草は、「もう草が少ないから終わり」と思われがちですが、実はとても重要です。 この時期にしっかりと管理しておくことで、翌年の春に生える雑草の量を減らし、草地の質を整えることができます。 また、寒暖差が大きくなる晩秋は、ヤギの健康にも気を配らなければなりません。 企業のCSR活動や自治体の地域事業としても、この季節の除草を上手に行うことは大きな意味を持ちます。


草の成長が止まる「今」が仕上げのタイミング
11月に入ると、ほとんどの草が成長を止め、茎が固くなります。 この状態のまま冬を越すと、春には枯れた草が発芽を妨げたり、害虫が繁殖する原因になります。 そのため、晩秋のうちにヤギが食べられる部分をできるだけ食べきることが大切です。 ヤギが食べ残した部分は、人の手で刈り取って「仕上げ除草」を行いましょう。 こうした小さな積み重ねが、翌春の草地環境を大きく変えます。 放牧面積を小さくしてムラをなくす
草が少ない時期は、ヤギが食べる場所にムラが出やすくなります。 放牧エリアを狭くして、1週間ごとに移動させるなど、区画を分けたローテーション放牧が効果的です。 ヤギが苦手な草への対処法
セイタカアワダチソウやススキなど、硬い草はヤギがあまり食べません。 そうした草は一度刈って柔らかい芽を出させたり、機械除草を併用したりして、地表の草密度を整えると良いでしょう。



寒暖差対策をしっかりと 晩秋は昼と夜の温度差が大きくなります。 ヤギが風邪をひかないよう、風よけの柵や簡易ハウスを設置しましょう。 雨の日や朝晩の冷え込みが強い日は、無理に放牧せず休ませることも大切です。 また、体が濡れたまま放置すると体温が下がるため、放牧後はできるだけ早く乾かしてあげましょう。 栄養管理で体力を保つ 草が減るこの時期は、栄養価の高い生草が少なくなります。 そのため、乾草や配合飼料を適度に与えることが欠かせません。 栄養が足りないと毛づやが悪くなり、体力も落ちてしまいます。 とくに繁殖を控えたメスや若いヤギには、タンパク質とミネラルをしっかり補うようにしましょう。


企業CSRとしての取り組み ヤギ除草は「自然と共生する企業活動」として注目されています。 燃料を使わずにCO₂排出を抑え、騒音や粉じんも出ないため、環境に優しい活動として評価が高まっています。 晩秋の除草までを年間スケジュールに含めることで、“継続的なCSR”として信頼を得ることができます。 また、秋は景観も美しく、写真や動画を使って広報活動を行うのにも最適な季節です。 自治体との連携で地域に貢献 自治体がヤギ除草を導入することで、公園や河川敷などの除草費用を削減できます。 さらに、地域住民が見学に訪れたり、学校で環境学習を行ったりと、人と自然をつなぐ場にもなります。



晩秋の除草を終えたあとは、翌年に向けた準備も忘れずに行いましょう。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 柵やネットの確認 | 壊れた箇所がないか点検し、冬の強風に備えます。 |
| 水場の管理 | 凍結や水漏れを防ぐ対策を行いましょう。 |
| 土地の休養 | 放牧を終えた区画をしばらく休ませ、草の再生を促します。 |
| 飼料の備蓄 | 冬に備えて乾草や配合飼料を多めに確保します。 |
| 写真・記録の整理 | 活動の様子を記録してCSR報告や広報誌に活用します。 |
こうした点を丁寧に行うことで、春のスタートをスムーズに迎えられます。


ヤギ除草は、ただの除草作業ではありません。 自然の力を借りて、地域や企業の環境を守る「サステナブルな管理方法」です。 晩秋の時期にしっかりと草を整え、ヤギの健康を守ることが、 翌春のきれいな景観と健やかな環境を生み出す第一歩になります。 企業にとってはCSR価値の向上に、自治体にとっては地域づくりの促進につながります。 ヤギが静かに草を食べる風景は、環境への優しさと未来への希望を象徴しています。